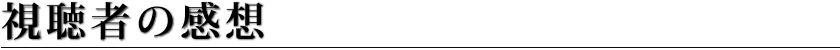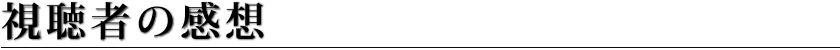

- 愛知教育大学 准教授
岩田吉生先生
- この映画は、今村さんと同じろう者が情報が制限された中で不安を抱えながら生活することの厳しさと、互いに支え合って力強く生きる姿を記録に収めた作品です。
今村さん自身、避難生活を送るろう者を記録する葛藤があったでしょうが、そこで暮らすろう者の思いと日常を、大勢の人々に知ってもらうために敢えてカメラを回し続けました。
この映画を通じて、ろう者の災害時の連絡体制、避難方法、避難所での生活支援の在り方等が見直され、行政や福祉の検討が進むことを強く願います。
皆さんで、この映画を観て、感じて、語り合いましょう。
- 気象庁地震津波防災対策室長
荒谷博さん
- 「津波の警報が聞えなかった」、「情報は命を守るもの」という聞えない人たちの声は、防災に携わる者の心を突き刺す言葉であった。
この映画は、我々が解決しなければならない課題を突きつけた作品である。
- ケイスケさん
- 普段は
①携帯電話
②財布
③煙草・ライター
④ハンカチ
⑤鍵
くらいしか持ち歩かない。
そこに小さいメモ帳・小さいペンを加えようと思ってる。
これで手話ができなくても筆談できる。
携帯を使えばいいけど、電池切れじゃ本末転倒だし。
先ずは架け橋になる土台作りから。
- 映画『うまれる』監督・プロデューサー
豪田トモさん
- 今村さんのテーマは「つながり」です。
聾(ろう)としての生を受けた事からか、なかなか人とうまくつながる事が出来ず、それがストレスになって以前はひきこもっていた事が多かったそうですが、ドキュメンタリー作りを通じて、人との関わりを彼女なりに探索しているそうです。
世界的にも聾(ろう)の映画監督は非常に珍しいので、彼女には今後もどんどん活躍していってほしいです♪
皆さまもぜひ応援よろしくお願いいたします!
-
http://www.umareru.jp/blog/2013/10/post-1142.html
- ダスキン愛の輪基金 事務局長
山本典芳さん
- 「架け橋 きこえなかった3.11」は、衝撃的なドキュメンタリー映画でした!
衝撃的な理由は、聴覚に障がいのある人たちにとって、警報による告知、刻一刻と変化する甚大な被害状況など、“事実を共有することの大変さ”を痛感いたしました。
一連の報道や遅ればせながら被災地現地を訪問して、被害状況や被災者の生活状況をある程度理解していたつもりでした。
今回の「架け橋」は、主人公(映画を見てのお楽しみ)を中心に、聴覚に障がいのある人たち独自の確認方法、復興に関する使命感が理解できました。
2年4カ月の取材を経て、世の中に“共生”を呼びかける貴重な映像として、感動しました。
- 海南病院 院長
山本直人先生
- 私自身、災害医療支援に赴きながら、ほとんど知ることが出来なかった事実があった。今村監督がろう者に寄り添うように描く映像は実に感動的である。
障害者や高齢者の方々は災害下では間違いなく情報弱者となる。
「災害・防災情報は全ての人に正しく迅速に伝えられるべき」そのためには、日頃からのコミュニケーションの絆を意識していかなければならない。
この映画はまさに、地域全体の架け橋であろう。
多くの方々にご覧頂きたいものです。